🌿50代で生き方を選び直した元公務員のあじっちです。
かつては「ちゃんとしなきゃ」「人との比較をこっそり」と思い詰めていましたが、今はもっと自然体で生きたいと思えるようになりました。
そんな私の再出発の記録が、どなたかの励みになれば嬉しいです。
夫が昨夜、仕事の資料をいくつも持ち帰ってきて、その様子を見て「ここまで家でやるんだ…」と改めて夫の体が心配になりました。
人との調整や資料整理、日々の業務も抱えながら、帰宅後もこうして仕事をしている。
本当に多岐にわたる業務を担っているのだなあと、しみじみ思いました
持ち帰り仕事が当たり前だった、かつての私
私自身も、かつて“公の職”に就いていたころ、
時間内に終わらない仕事を自宅に持ち帰るのは日常のことでした。
子どもを保育園や学童に迎えに行き、
夕食や家のことを済ませたあとに、スーパーのかごのようなバスケットに資料を詰めて──
誰にも見えないところで仕事をしていました。
職場にいないので、時間外手当も当然つきません。
それでも「この仕事は私がやるべき」と信じて、黙々と片づけていました。
「今は子育て中だから大変だよね」──
そんな何気ないひとことに、どれほど救われたか、今も思い出します。
組織の中の“見えない偏り”と仕組みの限界
職場には、良かれと思って任される業務の“偏り”がありました。
研修ではメンター制度や業務効率化の仕組みを学びましたが、
それが実務に活かされることはほとんどなかったように思います。
仕事を「できる人」に集めるほど、
その人も、確認する人も、どちらも疲弊してしまう──
本来なら、チームで支え合える体制が必要だったはずなのに、
当時の私は「仕組み」の足りなさに気づく余裕すらありませんでした。
FPで学ぶ「タックスプランニング」と制度のすきま
今日は、FPの勉強で「タックスプランニング」の分野に入りました。
青色申告や法人税、消費税、必要経費の考え方……
給与所得者とは違う視点から「経営」を知ることができました。
かつての職場では、備品や消耗品費など予算枠があり、食料費という数千円の配当もありました。
食料費のお茶代などは、足らないので自分たちで準備することも多かったです。
それでも──
- 暑い夏の日
- 肌寒い季節の夕方
- なんとなく疲れている方が来られたとき
心に寄り添ったお茶を一杯出すだけで、
空気がやわらぎ、心の距離も少し近づくのを感じていました。
「これは経費なのか、配慮なのか?」
その線引きに悩みながらも、本当に必要なことは何か──
今なら少し、わかる気がします。
息子の働き方に、時代の変化を感じる
息子の職場では、残業は事前承認制で、きちんと手当も出ます。
仕事量や時間の設計が、きちんと考えられているようです。
「働き方の文化が変わってきているんだな」と、しみじみ感じます。
今だから、感じられること
制度や仕組みは、時代とともに少しずつ進化していきます。
そのなかで、ただ制度を知るだけでなく、
- 誰かの負担を思いやること
- ちょっとした「配慮」を形にすること
そういったことができたら、
もう少しだけ、やさしい社会になるのかもしれません。
📚 FP・家計の学び直しを考えている方へ(PR)
私は他のFP講座を利用していましたが、
通信講座で効率的に学びたい方には、動画中心で学べる選択肢もあります。
※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。条件・内容は執筆時点の情報です。最新は公式サイトをご確認ください。
🌿 あじっちから皆さんへ
FPの学びを通して、昔の自分を思い出すことが増えてきました。
「なんでだろう?」と立ち止まる時間が、今の私にはあるからかもしれません。
昔の私と、今の私が、少しずつつながっていく。
そんな不思議な感覚を味わっています。
かつての頑張りや、人のやさしさに改めて気づけたとき、
それだけで、心がふわっとあたたかくなるものですね。
これからも、ゆっくり丁寧に学びながら、
自分の経験を、どこかの誰かの“灯り”にできたら嬉しいです。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました
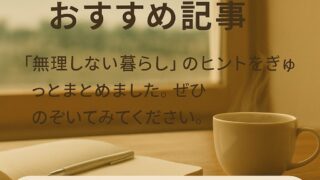
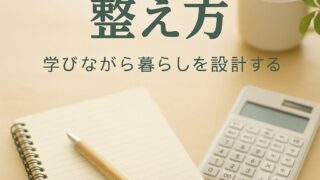
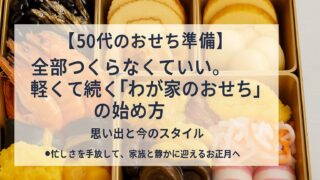
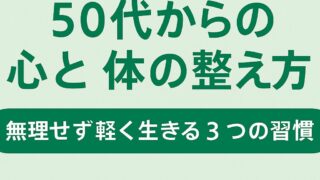

コメント