🌿50代で「ねばならない思考」を手放した元公務員のあじっちです。
無理しすぎて心も体もすり減ってしまった経験から、今は少し立ち止まることを大切にしています。
同じように「がんばりすぎてしまう」方に、ほんの少しでも気づきや安心が届けばうれしいです。
息子のバイク帰省に、言葉が出なかった日
息子がはじめて長距離のバイクで帰省します。
4月から県外で就職し、5月の連休に帰ってきて以来です。6月に「バイク買ったよ、バイクで帰るね」と言われて、「うっ」と絶句しました。
🚲息子の存在を冷静に考えても、「他に変わるものなどない自分の命より大事」と思っています。
そのことには、いつも変わりなくそう考えています。
でも、そんな息子も、もう、しっかり前を向いて自分の道を歩いています。
今回は、「息子のバイク旅」をきっかけに、
“心配”と“信じる”の間でゆれる、親としてのこころの景色を綴ります。
この記事で伝えたいこと
- 大切な人への“心配”を、どう扱えばいいのか
- 「止めること」と「信じること」のちがい
- 子どもが離れていく寂しさを、どうやって受け入れていくか
バイクで帰る息子と、昔のわたし
息子は学生最後の夏にバイクの免許を取りに行くと連絡があり、秋に取得しました。最初に驚いたことを覚えています。
その後もバイクは所有していませんでしたが、就職した今年の6月「バイクを買ったよ」と連絡がありました。
また軽く驚きました。夫は二度びっくりしていました。🚩関連する記事:
夫と私の気持ちは違っていたと想います。
夫はバイクと縁のない生活で、私は若い頃バイクに乗っていました。
そして夏休み休暇について、「バイクで帰るから」との連絡があり、流石にわたしも「やばいぞ、どうしたらいいんだろう」と心がざわざわしました。🚩関連する記事:
夫は「だめだ、危ない止めさせて」と。
息子の勤務地から我が家までは800km近くあります。
息子曰く、中間点で一泊する、帰りはフェリーを使うとのこと。
もう決定されたことのようでした。
あの頃のタンデムと、バイク事故
私がバイクに乗っていた頃、息子はまだ幼くて、「お母さんのバイクの後に乗りたい」とせがみました。
5歳の息子にヘルメットをかぶせ、背中から私のお腹にベルトをまわして、ヒヤヒヤしながら何度かタンデムしたこともあります。

私はバイクが好きだったし、安全に気を配れば危ない乗り物ではないことも理解しています。
でも、私がバイクを降りたのは事故を経験したからです。
一瞬の出来事でした。
だからこそ、バイクの危険性も知っているのです。
「反対する親」から「信じる親」へ
今回の帰省の件、「頭が痛いなあ」と当初思いました。
でも、成人した大人の息子に、今さら親が口を挟んでも……という想いが私には出てきました。
たぶん、私がまだ仕事をしていたら、こんなふうには考えなかったと思います。
いつも何かに追われていると、思考は止まらず、ぐるぐる巡ってしまうものです。
良い結論にたどり着かない思考ばかりしてしまっていたと、今になって思います。
働いていた頃の私なら
「バイク=危険=止めなきゃ」と即断して、夫と一緒に反対していたかもしれません。
でも、仕事をやめて暮らしが変わった今、自分にとって心地よい時間を過ごせていることが、心の断捨離にもつながっていると感じます。
息子の気持ちを想像してみたら
自分もバイクが好きなので、息子の立場にたって、いろいろ考えてみました。
- とにかくバイクに乗る時間がほしい
- 買ったバイクと過ごしたい
- 一人旅を通じて自由を感じたい
- 冒険のような体験をしたい
- 家族や友達に自分を見せたい
こんなふうに考えてるのかもしれないなと想ったら、息子のことなのに、私自身がわくわくしてきました。
心配は、親の孤独から生まれるのかもしれない
もちろん、心配は尽きません。
熱中症にならないか、下道でのトラブルは?帰省ラッシュの事故、バイクの前掲姿勢での体の負担などなど――
心配しはじめたらキリがありません。
でも、息子は「心配して」とは言ってきていません。
何かあっても、子どもの頃のように前の障害物を取り払うことは、**今の息子にとっては迷惑な“越権行為”**なのだと気づきました。
そっと、見守るということ
今の私にできることは、「後からそっと応援する」ことくらいです。
それはとても難しいけれど、でもきっと、それがいちばん信頼しているということなのだと、思うのです。
大事な人には、幸せだと感じる時間が多いといいな
自分にとって、無理なく心地よい時間が多いといいな
そう願っています。深く深く。
親の心配も、心の断捨離へ
子どもが成長していくと、親としての役割も、関わり方も、少しずつ変わっていきます。
それはときに孤独でもあります。
でも、それは「信じる」という優しい断捨離でもあるのかもしれません。
最後までよんでくださってありがとうございました。
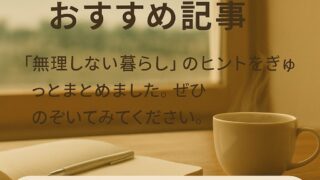
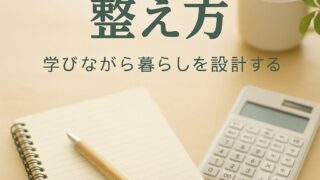
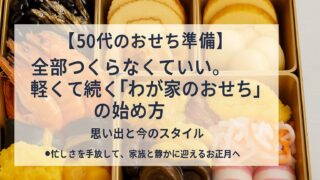
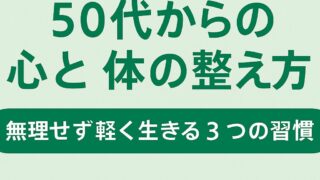

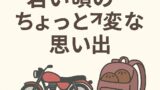

コメント