こんにちは、あじっちです。当ブログ にお越しいただきありがとうございます。
このカテゴリでは、心が軽くなる考え方や「こうあるべき」に縛られない生き方について、私自身の経験をもとに綴っています。
人との関係を大切にしてきた理由
私が「人とのつながり」を大切にしてきた背景には、小学一年生の冬に経験した“火事”があります。
家が全焼し、家族で近所の親戚の家に身を寄せました。祖母、両親、兄2人、そして私。
着の身着のままで、ただ燃える家を消火する様子を見つめていることしかできなかった――あの光景は今でもはっきり覚えています。
当時は幼く、状況の深刻さはよくわかっていませんでした。親戚の家に泊まることを、まるで旅行のように感じていた記憶さえあります。
でも、あのとき私たち家族が失ったのは、家やモノだけではなく、生活そのものでした。制服やパジャマ、歯ブラシや食器、布団やごはん……。すべてが焼け落ち、人様の力を借りなければ暮らせない毎日。
それでも、両親は焼け跡に新しい家を建て直しました。若くして大きな試練に立ち向かい、家族を支えた姿には、今あらためて尊敬の気持ちしかありません。
祖母はよく「人さまのおかげで生かされているんだよ」と言いました。
父は「人を大事にしなさい。自分の行いは巡り巡って自分に返ってくる」と教えてくれました。
火事の後、兄弟と一緒に毎日仏壇に手を合わせ、祖母の後ろでお経を唱える日々が続きました。
「怪我ひとつなかったのはご先祖様のおかげだ」と教えられながら、幼いなりに「感謝の気持ち」を覚えていったのかもしれません。
私はその言葉を受け止めすぎて、「人を大切にする」という教えを“極端なかたち”で実践してしまったところがあります。
0か1か、白か黒か――。中間がなく、寄り添うなら“とことん”寄り添いたい。
0.2や0.5ではなく、知ってしまったならもう知らないふりはできない。そんな思考のクセが、今振り返ると私を苦しめていた面もあります。
感情の振れ幅が大きかった子ども時代
子どもの頃、捨て犬を拾ってきては家族を困らせていました。お願いだから飼わせて、と。
小学2年のとき、やっと家族として迎えられた柴犬は、とても小さくて可愛らしい子でした。
でも当時の常識では、犬は屋内ではなく屋外で飼うのが当たり前。寒い夜は、こっそりこたつに入れてあげたり、自分の布団に招き入れたりしていました。
もちろん見つかって叱られるのですが、「寒いから」「かわいそうだから」と自分の気持ちを正当化していました。

やがてその犬が咳をし始め、私が高校に入学したばかりのころ、亡くなりました。
大きな喪失感でした。
あのときの私はまだ子どもで、「もう会えない」という事実をどう受け止めていいのかわからなかった。
現実を受け入れられず、もう一度姿を見たくて、土の下を探してしまった――
私は“感じる力”がとても強くて、
悲しみも、喜びも、他の人の痛みも、ふつうの何倍も受け取ってしまう。
それは時に、生きづらさにもつながるけど、
だからこそ見える世界があるのだとも思います。
やっと最近、わかったこと
私は「イレギュラー」にすぐには対応できません。
想定外の出来事や、感情の高まりがあると、思考と行動が追いつかなくなることがありました。
そのことで、生活の中で困ったり、人間関係に疲れたり、心が先にすり減ることもよくありました。
でも最近になって、「私はそういう人間なんだ」と少しずつ受け入れられるようになってきました。
昔は「なんでこんなことで疲れてしまうんだろう」と、
自分を責めてばかりでしたが、今は「感じやすい」「揺れやすい」ことを個性として見られるようになりました。
それだけでも、とても大きな一歩です。
🍀まとめ
火事の記憶や犬との別れ、人を大切にしてきた想い。
振り返ってみると、私の今の考え方や暮らし方は、あの経験たちがつながってできているんだなと感じます。
🌿こうして私はラクになれそうです
感情の振れ幅が大きい自分を「個性」だと思えるようになった今、やっと少しずつラクになってきました。
“こうあるべき”に無理に合わせるのではなく、今の自分に「うん、それでいいよ」と言ってあげられる。
そんな毎日を、大切にしていきたいと思っています。
誰かの気持ちに、そっと寄り添えたらうれしいです🍀
読んでいただいてありがとうございます。
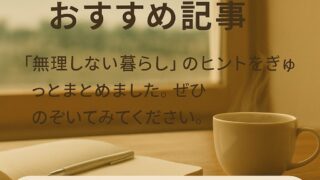
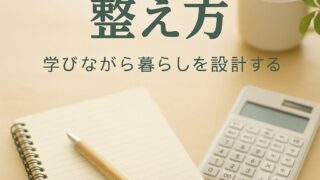
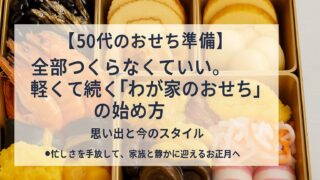
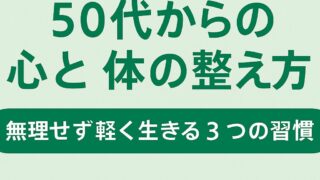
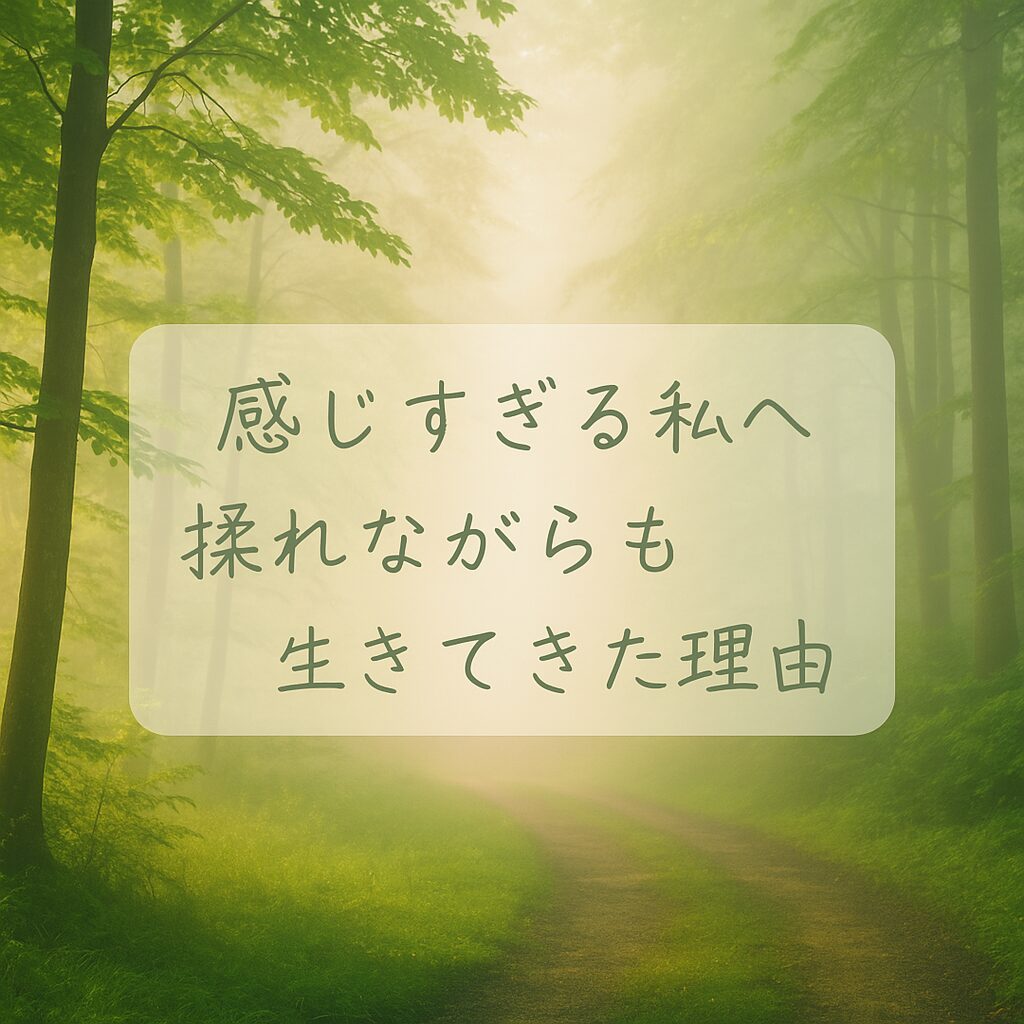
コメント