🌿50代で生き方を選び直した元公務員のあじっちです。
かつては「ちゃんとしなきゃ」「人との比較をこっそり」と思い詰めていましたが、今はもっと自然体で生きたいと思えるようになりました。
そんな私の再出発の記録が、どなたかの励みになれば嬉しいです。✅
FP2級を目指すことにした理由や背景については、FP日記 #0に書いています。
👉 【50代からのリスタート】FP日記 #0:50代、専業主婦の私が資格を目指す理由
昨日は気合いを入れて勉強を始めるつもりだったのですが…
いざ、いつもの机に座って、目の前に置いておいたFP2級の分厚いテキストと向き合うと、どうにも眠いのです。
とりあえずホンダさんのYouTubeを再生してみたものの、画面を見ていると眠気がどんどんやってくるんです。足をたたいてみたりしましたが・・・😢
「これはまずい」と思って氷たっぷりのお茶を飲んだり、コーヒーを飲んだりして、何とか乗り切ろうとしました。
一瞬だけ目が覚めた気がしましたが、またウトウトします…。😪
結局、初日に進んだのは「金融資産運用」の章の一部でした。
中学で習ったような「GDP」「日銀短観」「買いオペ・売りオペ」などを思い出して、懐かしい気持ちになったくらいでした。(中学ではないかもしれません🐧)
夜は、暑さのせいもあり夫も早めに布団へ。
私も19時45分にはテキストとパソコンを閉じ、エアコンの効いた部屋で早めに就寝しました。
「勉強できなかった…」と落ち込むよりも、「今日はここまで」と切り替えるようにするしかありませんでした。
少しだけ、でも確かな学び
そんな一日でしたが、ひとつ、印象に残った学びがあります。
それは「日本投資者保護基金」という制度のことです。
NISAやiDeCoを始めるとき、証券会社・銀行・郵便局など、いろいろな窓口がありますよね。
実は、証券会社が破綻した場合でも、最大1,000万円まで補償してくれる仕組みがあることを知ったんです。
これは「日本投資者保護基金」という制度で、証券会社を通じて投資をしている人のための安心材料です。
一方、銀行や郵便局、農協などを通じた投資は、「日本投資者保護基金」の対象外になるとのことです。
ただし、銀行が万が一破綻しても、顧客が保有している投資信託(受益権)は銀行の資産とは分けて管理されているため、原則として保全される仕組みになっています。
直接的な損失が出ることは通常ありませんが、事務的な混乱や補償の仕組みの違いから、「安心感の違い」を感じる方が多いのも自然なことかもしれません。
「そんなこと、今まで全く知らなかった…」とちょっと驚きました。
というのも、私は以前、郵便局や銀行の方に勧められて、手続きを進めようとしたことが何度かあります。
でも、途中で不備が出て頓挫したり、なんとなく止めてしまったりで…。
今になって思えば、ちゃんと調べて理解してから始めることの大切さを実感します。
夫も、まだNISAを始めていません。
「ちゃんと話を聞いて納得しないと始められない」と、慎重です。
それでも、ネット証券の良さを伝えていた私でしたが、今回の学びを通して、証券会社という選択肢の安心感も感じるようになりました。
学びのペースは遅くても、気づきは確かにある
こうして一つひとつ、生活の中の出来事と結びつけながら学ぶと、
「ああ、勉強して良かったな」と思える瞬間があります。
あと20日しかありません。
でも「眠くて勉強できなかった」と落ち込むより、「今日、ひとつでも知れたことがある」と思いたいです。(実はかなりあせっています😓)
それが、50代の私の“無理しない勉強スタイル”です。(あくまでも理想ですが😓)
📚今回の学びメモ:
- 金融資産運用:GDP・日銀短観・オペレーションなど
- 日本投資者保護基金の存在と、その対象になるのは証券会社だけという点
最期まで読んでくださってありがとうございました。
📚 FP・家計の学び直しを考えている方へ(PR)
私は他のFP講座を利用していましたが、
通信講座で効率的に学びたい方には、動画中心で学べる選択肢もあります。
※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。条件・内容は執筆時点の情報です。最新は公式サイトをご確認ください。
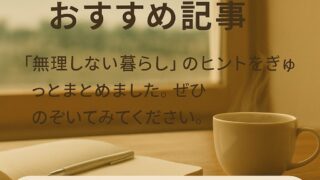
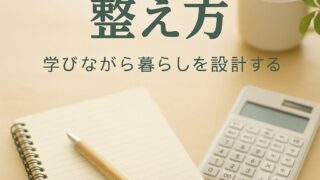
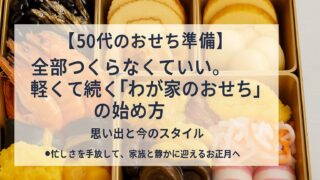
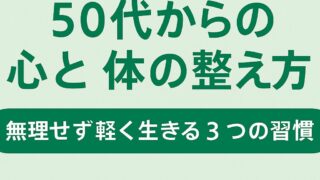

コメント