※私は現在FP2級資格取得に向けて勉強中です。記事内容は学習に基づいた情報提供であり、資格を持った専門家としての助言ではありませんのでご注意ください。
こんにちは、あじっちです。
今日は、FPの「相続・事業承継」分野の勉強をしていて、父が亡くなったときのことを思い出しました。
私自身の体験と、FPの知識が重なって「今知っておけば、あのときの気持ちは少し違っていたかもしれない」と、そんな想いを綴ってみたいと思います。
この記事は…
・親が亡くなったあとに、何をどう手続きすればいいか不安な方
・相続放棄や準確定申告について、実際の体験談が知りたい方
・FP2級を勉強中で、リアルな相続の場面を想像したい方
に向けて書いています。
「おかえりなさい」が心に響いた朝
今朝、夫の出勤を見送るために駐車場へ出たとき、しばらく不在だったお隣さんの車が戻っていました。
顔をよく知らないお隣さんですが、思わず「帰ってきたね!」と夫と声を合わせてしまいました。
変化に弱い私は、日々の小さな変化にも心がざわついてしまいます。
手乗り文鳥の「シロ」も、夫がいないと落ち着かず、私の腕や足にそっととまってじっとしているようになります。
私も、そんな「シロ」に似ているのかもしれません。
FPの学びと、自分の体験が重なる瞬間
FPの相続分野の勉強をしていると、ただ制度を覚えるだけでなく、自分の体験と重なる部分が多く、ひとつひとつが心に響きます。
たとえば「配偶者居住権」。
父が亡くなり、母が実家で一人暮らしをしていることが、まさにこの制度に当てはまります。
母が安心して住み続けられるという仕組みがあると知って、制度の優しさを感じました。
父の「確定申告を頼むよ」が心に残っている
父は亡くなる少し前まで、畑で農作物を育てて道の駅に出荷していました。
そして私にこう言っていました。
「申告の書類はあそこにあるから、頼むよ」
当時の私は仕事で忙しく、深夜にレシートや伝票をまとめてエクセルに入力しながら「わからないよ」と泣きたくなる思いで作業をしていました。
結局、税務署に問い合わせたところ「申告の必要はない」と言われて安心したものの、住んでいる自治体から後に確認の通知が届き、焦った経験もあります。
知識があれば、もう少し落ち着いて対応できたのかもしれません。
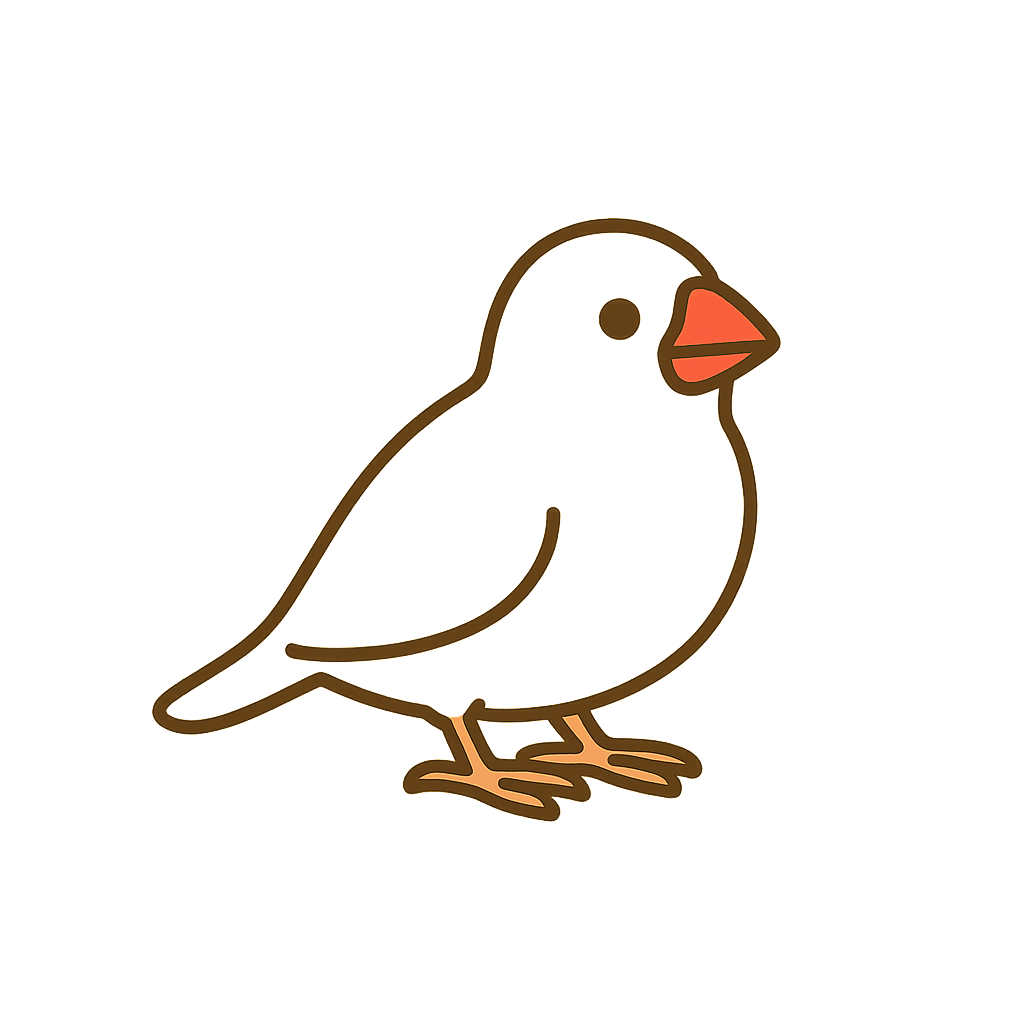
詳しく教えてあじっち!「準確定申告」って?

故人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得について、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に申告・納税する必要があります。父のように農作物の出荷利益(事業所得または雑所得)があった場合、原則としてこの準確定申告が必要になります。
本当に伝えたかったのは、「父の願いを叶えたかった」
申告をきちんとすべきだったと思うのは、事務手続きとしてではありません。
それが、父が私に託した「願い」だったからです。
あれが、最後の親孝行だったかもしれないな――。
今思い返すと、そんな気持ちになります。
相続放棄も知らなかった私
私は遠く離れた場所で暮らしているため、父の亡きあと、相続に関する書類のやりとりが本当に大変でした。
「相続放棄」という制度を知っていれば、選択肢が増えていたかもしれません。
相続は頻繁に経験するものではありません。
でも、いざというときに慌てないためにも、少しだけでも知識があると「心のざわつき方」が違うのだと、今回の勉強で気づかされました。
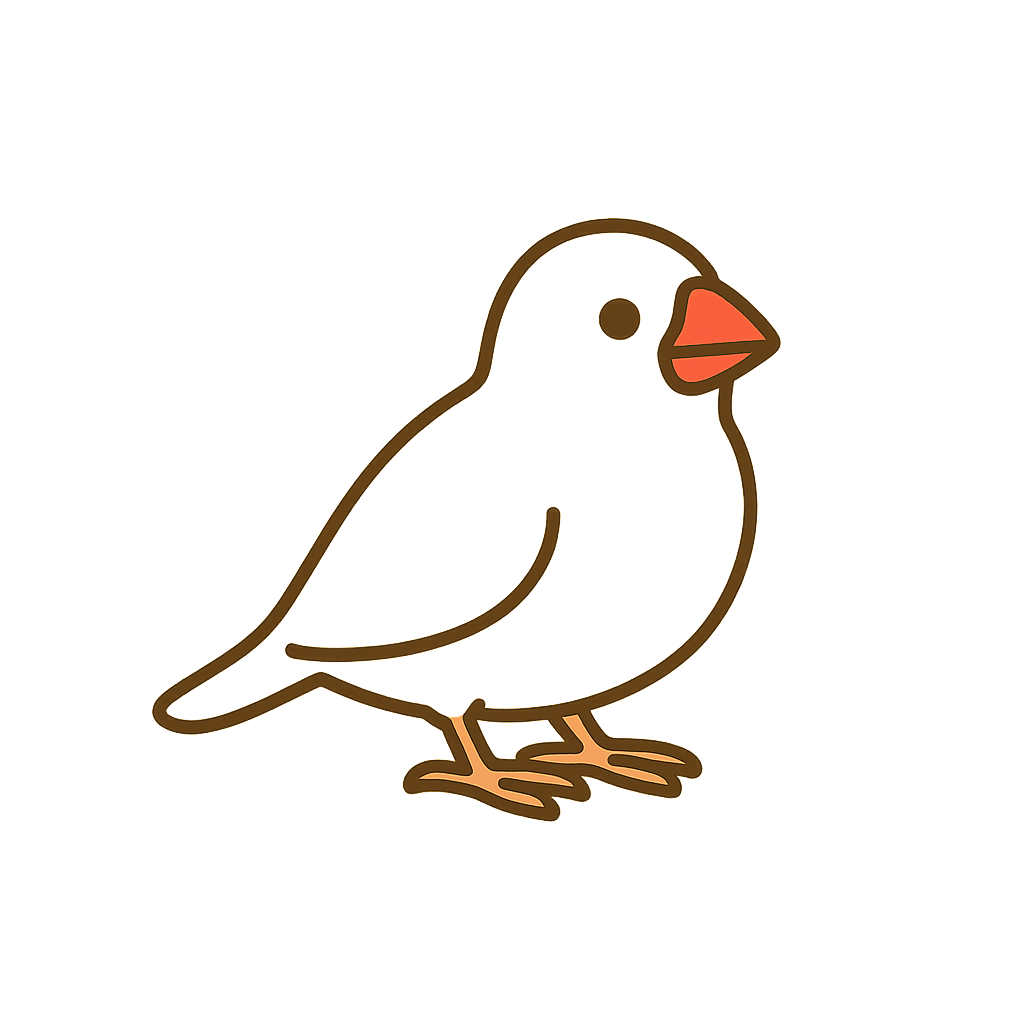
詳しく教えてあじっち!「相続放棄」って?

故人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も含む全て)を一切相続しない、という意思表示です。相続の開始を知った日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
今の自分ができること
父のこと、母の今、そして自分のこれから。
すべてに「お金」は関わっていて、その知識を学ぶことが、結果的に家族や誰かを支える力になるのだと実感しています。
相続、贈与、税のこと…。
それらはすべて冷たい制度ではなく、使い方次第で「人を守るやさしさ」になるのかもしれませんね。
あの夜の、レシートと格闘した私の時間も貴重だと、今はそう思っています。
📚 FP・家計の学び直しを考えている方へ(PR)
私は他のFP講座を利用していましたが、
通信講座で効率的に学びたい方には、動画中心で学べる選択肢もあります。
※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。条件・内容は執筆時点の情報です。最新は公式サイトをご確認ください。
あじっちから皆さんへ
私のように、経験してから「あのとき知っていれば…」と思う方がいなくなるように。
今学んでいるFPの知識を、これからもわかりやすくブログで共有していけたらといいなと思っています。
自分の気持ちを整理しながら、誰かの役にも立てたら――
そんな気持ちで書いています。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました。
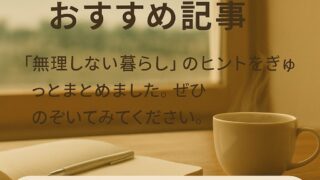
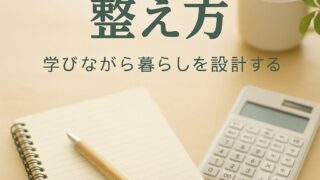
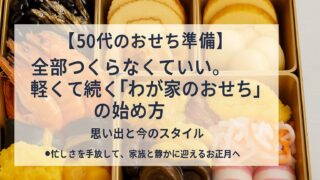
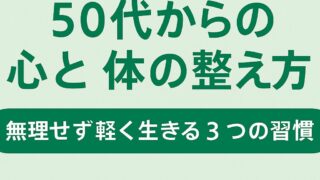

コメント