🌿 無理しない暮らしを選びなおした50代、元公務員あじっちです。
なんとなく、「うん?」と思ってきた感覚。
私が考えるようになったきっかけは、夫がくれた一冊の本でした。
1. 夫から「HSPかもしれない」と言われたきっかけ
・10年前に渡された一冊の本
ある日、仕事から帰ってきた夫が、私に一冊の本を差し出してこう言いました。
「これ、あじっちに当てはまらないかな? こういう病気があるらしいよ」
彼が手にしていたのは、**HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)**について書かれた本でした。
読みやすく、「この項目に5つ以上当てはまれば、あなたもHSPかもしれません」といった簡易チェックもありました。
読んでみると、いくつも思い当たる節がある一方で、「それはちょっと違うかも…?」という項目もありました。
・自己診断の結果と感じた違和感
たとえば、「蚊も叩けないときがある?」というところには、「いや、それは叩く。むしろ私が真っ先に叩く」って(笑)。
「言いたいことが言えない」という項目にも、確かに我慢して飲み込むこともあるけれど、逆に言いすぎることもあるな…って思いました。論破することも。
でも、全体を読み終えて感じたのは、「これ、たしかに当てはまってるかも」という、腑に落ちるような不思議な感覚だったように記憶しています。
2 .HSPって診断名なの?病気なの?
・世間で広がる“繊細さん”という呼び方
世間では“繊細さん”という呼び方で、HSPという言葉もずいぶん広まっていますよね。
本屋さんにも「HSPの生き方」や「繊細な人のための~」といった本が並び、SNSでもよく見かけます。
「何か特別なひと」のような、みんなその人に気を遣って接しないといけないような、そういう風潮があるんですかね。
人はそれぞれ、生まれながらに持っているものや、後で備わったもので現在の自分が成り立っているのだと思います。
「遺伝と環境=現在の私」みたいな。
私は、仕事をやめて、体の健康を取り戻すとともに、ざわつく心も落ち着けたいと考えながら過ごしています。
YouTubeでは、精神科医・益田祐介先生の番組をよく見ています。←(これも街録チャンネルに出演されていたことで知ったのですが。)
益田先生がYouTubeを始めたきっかけは、
「診察時間がわずかなので、紙に書いて気づきを渡していたけど、患者さんは捨ててしまう。
患者さんから“YouTubeで配信して、心や脳のしくみを教えてほしい”と言われて病気の解説を始めた」
とのことでした。
この番組では、私たちが日常で感じる些細な想いや、専門的な精神科の病気、脳科学に至るまで幅広く発信されています。
・精神科医・益田祐介先生の見解とは
HSPは病気でもなければ診断名でもない。
感じやすい気質が際立ったものや、極端に顕著で、その中で生きづらさを感じる人がいる。
人には、感受性が高すぎる人もいれば、低すぎる人もいる。
しかし、感覚が過敏であることを精神医学的にはHSPという病気とは位置づけていない。
基礎的な疾患の表れとして感覚過敏が出ることもあり、
たとえば、うつ病や社交性不安障害、回避性パーソナリティ障害を持つ人には、そのような症状が出ることもあり、
「繊細さん」と言われることが多い。
便利なことばかもしれない。
また、発達障害を持つ人にも多い。
つまりHSPは、
「気質」や「傾向」として捉えるものであって、医学的な分類ではないという
3. 「HSPだから」と片づけてしまいそうな私へ
私自身、自分が心や脳の振れ幅が大きいことで困ることもありますが、
「繊細さん」という言葉に、自分を当てはめて“片付けて”しまっていないかと思うことがあります。
SNSや情報サイトでは、まるで診断のように扱われていたり、
「私はHSPだから」と自己紹介のように使っていたりするのを見かけることがあります。
それ自体が悪いことではありませんが、それだけで安心してしまうことに、ちょっとした危うさを感じたんです。
・自分の感受性のルーツをたどって
思い返せば、私は子どもの頃から感受性が強かったと思います。
特に記憶の鮮明さや、「気配を感じ取る」ような自分なりの感覚がありました。
たとえば小学生のとき、真夜中に波の音が聞こえた瞬間、「津波がくるんじゃないか」と強い不安に襲われたことがあります。
布団をかぶって音を遮ろうとしても、心臓の音がドクンドクンと響いて、ますます不安が大きくなっていく……。そんな夜が何度もありました。
・火事の記憶と不安感のつながり
もしかしたら、幼い頃に経験した火事の記憶が、私の中に強く残っていたからかもしれません。
家族と過ごしていた家が突然の火事に見舞われ、私は一人、家の中に取り残されてしまいました。
当時の記憶は、今でもはっきりと思い出すことができます。
ただ、それがトラウマとなり、感覚過敏の原因だとは誰も証明できません。
あくまで、それは「私の身の上に起きた出来事」であるということです。
私は、感じる自分の受け止め方が人と違うことを自覚していますし、
その強さは、これまでの環境的な要因+生まれ持った気質の掛け合わせで形づくられていくのだと思っています。
4.「HSPって言えば安心」の落とし穴
・「HSP=安心」の先にある停滞
HSPという言葉に出会ったとき、「ああ、これでやっと説明がつく」と思ったのは確かです。
でも、それだけに頼ってしまうと、自分を深く見つめることをやめてしまいそうになる。
たとえば「HSPだから人混みが苦手」「HSPだから疲れやすい」といったふうに、自分をラベリングしてしまうと、
自分の弱さに理由ができた代わりに、どう向き合っていけばいいかが見えなくなることもあるのではないでしょうか。
・専門的な視点と、自分をていねいに知るということ
何か、指標が必要だとすれば、学びや本質の中からそれらを得なければならないと思っています。
益田先生のような専門ドクターに受診して、適切な処置やアドバイスをもらうことが大事だと考えています。
「私は私。何がつらいのか、どうすれば心地よく生きられるのか」
――そんな視点のほうが、きっと私には合っているように感じています。
5.「繊細であること」は弱さじゃない
・音・匂い・空気に反応するわたしの感覚
私自身、音や匂い、人の気配にとても敏感です。
電車の中や買い物に行くときは、イヤフォンで音を流して、自分の世界にいるようにしています。私はそれでラクになれるのです。
匂いも同様で、今は一人で過ごすことが多いので困りませんが、苦手な匂いに出会うと、体が反応して気分が悪くなることもありました。
また、人の言葉の裏にある「ちょっとした違和感」を自分なりに解釈してしまったり、
空気の変化にざわっと心が反応してしまうこともあります。
でもそれって、悪いことばかりではないんですよね。
- 誰かの痛みに気づけること
- 自然の変化に敏感でいられること
- 言葉を大切に選べること
・敏感さは“洞察力”であり“才能”でもある
そういう細かさは、「弱さ」ではなく「洞察力」や「才能」として、自分の中にあるのだと思うことにしています。
それでも、まだまだ「生きづらいなあ」と感じる場面は多いんです。
だから、**その繊細さとうまく付き合っていく方法を探すことが、私の“再出発”**でもあるのです。
6. まとめ:「HSP」より「私は私」として生きる
・ラベルより、自分の声に耳をすませて
「HSPって言えば、なんかカッコがつく気がしてた」
――そんなふうに思っていた頃もありました。
でも今は、HSPという言葉を“説明書”ではなく、“ヒント”として使うくらいがちょうどいいと思っています。
もしかしたら読んでくださっている方の中にも、「ちょっと生きづらいな」と感じることがあるかもしれません。
そんなとき、誰かが名づけた言葉を探すより、まずは自分自身の声に耳を傾けて、深呼吸をする。
そうすれば、一旦その“ぐるぐる思考”の場から離れることができます。
・自分にとっての“心地よさ”を見つけていく
感じ方は、個性のようなもので、その人らしさのひとつです。
無理に変えなくてもいいと思います。
ただ、自分がどうしたらラクにいられるのかを、丁寧に見つけていけたらいいなと思います。
読んでくださってありがとうございました。
この記事もおすすめです
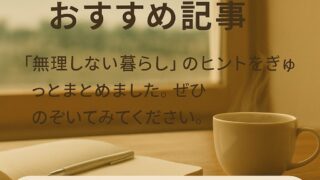
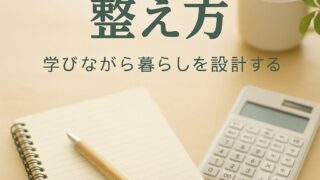
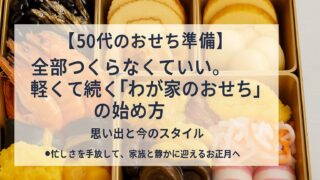
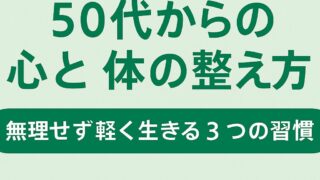


コメント